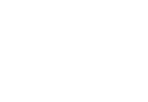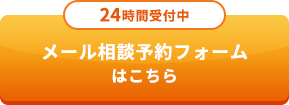【判例解説】「遺言能力と遺言の有効性」 東京高等裁判所平成25年3月6日判決
今回は、本判決を通じて、普段あまり聞きなれない「遺言能力」という言葉について、お話ししたいと思います。
1 事実の概要
昭和55年4月、Aさんは、全財産を妻Bに相続させるとの自筆証書遺言(以下「旧遺言」といいます。)を作成していました。
ところが、それからしばらく経過した平成19年3月2日に、Aさんは、財産を妻Bではなく妹のXに相続させるとの公正証書遺言(以下「新遺言」といいます。)を残していました。
その後、Aさんは死亡し、Aさんの相続人は、妹Xと、弟等のYらとなりました。
民法1023条1項によれば、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」ことになりますから、新遺言が有効であれば、旧遺言は撤回されたことになり、Aさんの財産は全て妹Xが相続することになります。
そのため、妹XはYらに対し、新遺言が有効であることの確認を求める訴訟を提起しました。
2 本判決の争点
本判決の争点は、Aさんの「遺言能力」の有無です。
遺言能力とは、「遺言者が遺言事項(遺言の内容)を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力(意思能力)」をいいます(東京地方裁判所平成16年7月7日判決)。
簡単に言えば、自己の財産を遺言によってどのように相続させるか自分で決定することができ、遺言を作成することがどのような効果をもたらすのか理解できる能力です。遺言は法律行為であるため、遺言作成時にこのような遺言能力を有していなければ、遺言は無効となります。
そのため、本件では、新遺言作成時にAさんが遺言能力を有していたかが争点となっているのです。
3 裁判所の判断
⑴ 第1審(原審)
本判決の原審は、新遺言作成当時、Aさんが認知症に罹患していたものの、遺言能力を欠く程度のものではないこと、公証人がAさんの意思と新遺言の内容が合致していることを確認していること、当時妻Bは末期がんで入院しており、その世話をしていたのは妹Xのみで、旧遺言の内容変更を希望することは十分あり得ること等を理由に、新遺言は有効であると判断しました。
⑵ 第2審(本判決)
ところが、本判決は、Aさんは新遺言作成時に、認知症や薬剤の影響で判断能力が減弱した状態であり、意思能力がなかったと考えられるため、特段の事情のない限り、遺言能力が無いと推認させると判断しました。
その上で、特段の事情の有無について検討し、妹XはAさんが新たに遺言を作成したいとの話を聞いていないのに、新遺言作成手続を行ったといえること、公証人の作成手続も本人確認等が不十分であったこと、新遺言作成当時は妻Bが存命中にもかかわらずあえて妹Xに財産を全て相続させる内容に変更する合理的な理由が見当たらないこと等の理由から、遺言能力を認めるべき特段の事情があるとはいえないと判断しました。
4 遺言能力の判断基準
(1)遺言能力の有無
遺言能力の有無は、遺言者の能力の程度の問題であるため、様々な事情を考慮して判断されます。
そのため、明確な判断基準はありません。
もっとも、一般的には、①遺言時の遺言者の心身の状況、②遺言内容、③遺言の動機・理由・経緯等を総合考慮して判断されています。
①遺言時の遺言者の心身の状況
このうち、最も重視されるのは、①遺言時の遺言者の心身の状況です。
これは、遺言当時の医療記録(カルテや診断書等)を証拠として、遺言能力の有無を立証することが考えられます。
また、遺言の方式が公正証書遺言であると、遺言書の作成に公証人と証人が立ち会い、基本的には本人の意思と遺言の内容が合致していることが確認されます。
公証人の証言等の信用性は一般的に高いとされていますので、公正証書遺言が作成された事実は、心身の状況に問題が無いとして遺言能力を認める方向に傾く事情といえます。
②遺言内容
②遺言の内容については、内容が複雑なものであれば、遺言者にはより高度な能力が要求されることになります。
そのため、遺言の内容が多岐にわたり、債務の精算等の複雑な計算を要する様な場合では、これを理解するだけの能力が無かったとの立証を行いやすくなるため、遺言能力を否定する方向に傾く事情といえます。
③遺言の動機・理由・経緯等
③遺言の動機・理由・経緯等については、例えば、それまで疎遠だった親族に対し、突然全財産を相続させる旨の遺言を残したような事情があれば、そのような内容の遺言をすることは不自然であるとして、遺言能力を否定する方向に傾く事情といえます。
(2)本判決
本判決は、まず①遺言時の遺言者の心身の状況について検討し、原審と異なり、特段の事情が無い限り、遺言能力は認められないと判断しました。
そのため、本判決でも、①遺言時の遺言者の心身の状況を最重視していることがわかります。
その上で、②遺言の内容、③遺言の動機・理由・経緯について検討し、特段の事情も認められないとして、妹Xの請求を棄却したと考えられます。
5 遺言、特に公正証書遺言の無効を主張することは容易でないこと
先程触れたように、公正証書遺言の場合には、公証人の証言等の信用性が一般的に高いとされており、遺言作成時にそのような公証人のチェックが入るため、類型的に、遺言能力を否定することが困難であることが多いといえます。
実際に、本判決では、公証人において、Aさん本人の自宅住所確認が不十分であったこと、作成手続きに新遺言で利益を受ける妹Xを同席させていたこと、Aさんの署名の可否を試みていないこと、Aさんの視力障害に気付いていなかったこと等の事情を細かく認定していますが、ここまで細かい認定が必要なほど、公証人の証言等の信用性を否定するのは難しいということが読み取れます。
また、さらに本判決の結論について注意しなければならないのは、本判決の事例では、①遺言時の遺言者の心身の状況について、検討する医療記録が証拠として充実していたという点です。
たとえ公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言の場合であっても、①遺言時の遺言者の心身の状況を裏付ける医療記録等の客観的証拠が乏しければ、遺言能力を否定することは困難といえます。
例えば、遺言作成当時、認知能力が低下していたことは確かだけれども、それを裏付ける医療記録が存在しないというような事例では、最も重要な①遺言時の遺言者の心身の状況について証明することが困難であると言わざるを得ません。
そのため、遺言能力について裁判所に判断を求める際には、特に公正証書遺言の場合には、事前に遺言作成当時の状況や、手元にある資料等の入念な検討が必要であると言えます。
6 終わりに
遺言は亡くなられた方による、残された方々への最後のメッセージです。
そのため、遺言に関する判断は、できる限り亡くなられた方の意思を尊重した形で行われなければなりません。
一方で、遺言作成時に遺言能力が存在しなかった場合のように、亡くなられた方の意思が反映されたものでない可能性のある遺言については、その有効性を争うことも検討されてしかるべきです。
もっとも、先に述べさせていただいたように、遺言の効力を争うには、遺言作成当時の状況や証拠資料の検討が重要となってきます。お困りの際は、当事務所をお気軽にご利用いただけますと幸いです。
以上