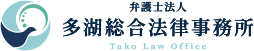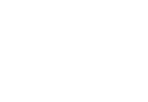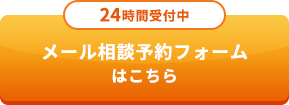【弁護士による判例解説】「自筆証書遺言として有効な方式とは」東京高裁令和元年7月11日判決等
遺言は、法律上、①自筆証書、②公正証書、③秘密証書のいずれかの方法によってしなければならないと定められています(民法967条)。
今回は、このうち、自筆証書の方法による遺言について、自筆証書遺言の方式を満たすと認められた事例、認められなかった事例を通じて、どのような形式を備えることが必要であるかをご説明いたします。
1 法律上の要件
自筆証書遺言の法律上の要件は、以下のとおりです(民法968条)。
- 遺言者が、本文・日付・氏名を自書し、押印すること
- 財産目録は自書でなくても良いが、目録の全ページに署名捺印すること
- 遺言書の加除変更は、遺言者が変更した旨を付記して署名捺印すること
自筆証書遺言に押す印鑑は、実印である必要はなく、本人のものであるとわかれば、指印でも良いとされています(最高裁判所平成元年6月23日判決等)。
また、2番目の、財産目録は自書でなくても良いというのは、平成31年1月に施行された改正民法で新しく定められた内容です。
それまでは、自筆証書遺言は全て自書する必要がありましたので、財産が多く、複雑な場合には作成するのが大変でしたが(もっとも、そういった場合には、公正証書遺言を活用することが多いかもしれません。)、若干、自筆証書遺言の作成の要件が緩和されたとも言えます。
以下では、自筆証書遺言として有効であるかどうかが争われた事例について、有効と認められたもの、認められなかったものを、いくつかご紹介いたします。
2 「証書性」が問題となった事例
⑴ 東京高等裁判所令和元年7月11日判決
被相続人が、生前、相続人Aに対し、ハガキで「マンションはAにやりたいと思っている。」と書いて送ったものが、自筆証書遺言と言えるかどうかが問題となった事例です。
ハガキには、被相続人の氏名と日付が書かれ、被相続人の指印も押してありました。
Aとしては、このハガキが有効な自筆証書遺言であるとして、マンションの取得を主張しましたが、裁判所は、「その表現ぶりのほか、控訴人に対する私信の中の記載であることに照らせば、本件マンションを控訴人に取得させたいという希望ないし意図の表明を超えるものではなく、少なくとも本件マンションを控訴人に遺贈するとの確定的、最終的な意思の表示であると断定するには合理的な疑いが残るところである。」として、自筆証書遺言としての有効性を否定しました。
⑵ 東京高等裁判所平成2年8月7日判決
「自筆証書遺言」という表題のもと、財産の承継人を定める事項を内容とする本文と、被相続人の氏名、日付の記載と捺印がある文書に加除修正の書き込みがなされ、遺言書の書き方に関する週刊誌の切り抜きと一緒にホチキス留めされ、紙面の裏側には「自筆」「公正証書」「証人二人」などの書き込みがあるものについて、自筆証書遺言として有効であるかが争われた事例です。
判決では、一見して雑然とした印象を受け、下書きであったと疑う余地もあるけれども、加除修正によって遺言書全体が毀滅されたに等しい影響を受けるものではなく、書き込みによって本文自体の判読が不可能になっているものでもないなどの理由を挙げ、自筆証書遺言としての有効性を肯定しました。
加除修正が法律上の要件に従ってなされておらず、修正された部分の中には「ある不動産を誰に相続させるか」という遺言書の核心ともいえる部分の修正が含まれていた事例であるため、有効性を肯定した結論には、個人的には少々疑問が残るところです。
3 「日付」の記載が問題となった事例
⑴ 東京地方裁判所平成28年3月30日判決
意図的に日付を遡って作成した遺言書が、自筆証書遺言として無効であると判断された事例です。
ただしこの事例は、被相続人が認知症と診断された後で、相続人の一人が遺言書の作成に関与していたことが強く疑われる事例であり、そのような事情も踏まえて、遺言能力等の問題に立ち入ることなく、「日付について法律上の要件を満たさない」という形式的な要件で判断したのではないかとも考えられます。
⑵ 最高裁判所昭和54年5月31日判決
自筆証書遺言の日付を、「昭和四十壱年七月吉日」と記載した自筆証書遺言については、暦上の特定の日を表示するものとは言えず、自筆証書遺言としての法律上の要件を欠くとして、無効であると判断されました。
ついつい「吉日」と書いてしまいたくなる気持ちもわかりますが、この他にも、「吉日」と記載して無効になってしまった裁判例がありますので、自筆証書遺言を作成される際には特定の日付を記載するよう、ご注意ください。
⑶ 最高裁判所昭和52年4月19日判決
自筆証書遺言の日付以外の部分を作成した8日後に、当日の日付を記入した遺言書は自筆証書遺言として有効である、と判断された事例です。
遺言の日付は、成立の時期を明確にするため必要とされているという趣旨から、日付を記入した日に遺言が成立したことが明確である以上、法律上の要件に欠けることはないと判断されました。
日付を遡って記載したわけではないという点において、⑴で紹介した事例とは異なります。
4 「氏名」が問題となった事例
⑴ 東京高等裁判所平成18年10月25日判決
カレンダーの裏に「遺言書」という表題で書かれた文書には署名押印がないものの、その紙が封入されていた封筒には署名押印があるというケースで、裁判所は、文書と封筒が一体のものとして作成されたと認められるのであれば、自筆証書遺言として有効なものと認める余地があるとした上で、検認(裁判所において、自筆証書遺言を確認する手続き)の時点で封筒が開封されており、文書と封筒の一体性が明らかでないとして、自筆証書遺言の有効性が否定された事例です。
封筒が開封されてさえいなければ、自筆証書遺言として有効と判断できるどうかはわかりませんので、「本文ではなく封筒に署名押印をして封をしておけば良い」と考えるのは危険かもしれません。
⑵ 神戸地方裁判所昭和47年9月4日判決
遺言者が何者であるかが明らかであれば、署名は戸籍上の氏名である必要はなく、また、氏名の一方でも足りると判断された事例があります。
ただ、この事例の遺言者は元々無国籍のロシア人であり、帰化して日本風の戸籍上の氏名を取得したものの、遺言書の署名には帰化前の氏名を用いたという特殊な事例です。
「自筆証書遺言の署名は戸籍上の氏名でなくても良い」とはいえ、通称として浸透している氏名であれば許されるのか、どういう状況であれば浸透していると言えるのか等、様々な問題が生じかねませんので、後に疑義が生じないようにするためには、自筆証書遺言は戸籍上の氏名で署名するのが無難でしょう。
5 まとめ
以上、ご紹介したように、自筆証書遺言の要件は法律で決まっていますが、その要件を満たしているかどうかを判断するには、様々な解釈があり得ます。
ただ、解釈が分かれて相続人間で紛争になり、結果として遺言書の内容を実現できなくなってしまっては、遺言書を作成する意味がありません。
遺言書を作成するに当たっては、法律上の要件を充足するようによく気を付けていただく必要があり、遺言の効力をより確実なものにするためには、形式的要件が問題になり難い公正証書遺言の作成を検討することをお勧めいたします。