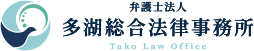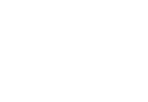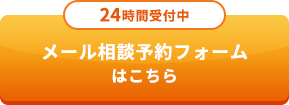【弁護士による判例解説】「共有分割は最後の手段」 大阪高等裁判所平成14年6月5日決定
今回は、遺産分割の方法の一つである共有分割についてご説明します。
1 遺産分割の方法の種類
遺産分割の方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、そして④共有分割があります。
①現物分割とは、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割する方法です。
たとえば、兄弟二人による遺産分割において相続財産として土地Aと土地Bがある場合、土地Aを兄に、土地Bを弟に取得させる場合です。
②代償分割とは、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させた上で、代償金の支払いという形で他の相続人に対する債務を負担させる方法です。
たとえば、兄弟二人による遺産分割において相続財産として2000万円の土地を兄が取得する場合に、兄が弟に対して1000万円の代償金支払債務を負担する場合です。
③換価分割とは、遺産を売却等で換金した後に、価格を分配する方法です。
たとえば、兄弟二人による遺産分割において、相続財産である不動産を2000万円で売却し、1000万円ずつ兄弟で分ける場合です。
④共有分割とは、遺産の一部、全部を具体的相続分による物権法上の共有取得とする方法です。
たとえば、兄弟二人による遺産分割において、相続財産として一つの土地がある場合に、土地を兄弟で一人ずつ共有状態として分割を終わらせる場合です。
2 なぜ共有分割は最終手段とされているか
たとえば兄弟二人による遺産分割において、相続財産である不動産をどのように分けるか話がまとまらないときに、2分の1ずつ共有することにしましょうという分割は、スムーズな解決のようにも思えます。
しかし、裁判例は、共有分割による分割方法は最終手段としています。
本判決の原審は、相続財産の一部の不動産について、共有分割とすべきと判断したのですが、本判決は次のとおり判断して、原審に差し戻しました。
「遺産分割は、共有物分割と同様、相続によって生じた財産の共有・準共有状態を解消し、相続人の共有持分や準共有持分を、単独での財産権行使が可能な権利(所有権や金銭等)に還元することを目的とする手続であるから、遺産分割の方法の選択に関する基本原則は、当事者の意向を踏まえた上での現物分割であり、それが困難な場合には、現物分割に代わる手段として、当事者が代償金の負担を了解している限りにおいて代償分割が相当であり、代償分割すら困難な場合には換価分割がされるべきである。」
そして、「共有とする分割方法は、やむを得ない次善の策として許される場合もないわけではないが、この方法は、そもそも遺産分割の目的と相反し、ただ紛争を先送りするだけで、何ら遺産に関する紛争の解決とならないことが予想されるから、現物分割や代償分割はもとより、換価分割さえも困難な状況があるときに選択されるべき分割方法である。」
本判決は以上のように述べて、「原判決は、以上と異なり、共有・準共有状態の解消も比較的容易であろうとの理由付けで、ほとんど全部の遺産を共有としたものであるが、共有・準共有状態の解消が比較的容易なのであれば、遺産分割においてその解消を行うべきであるから、原審判の命じた遺産分割は到底容認できるものではない。」と判断し、「原審判は、その選択した遺産分割の方法が相当ではないから取消しを免れない」と判断したのです。
このように、裁判例は、共有分割は紛争解決の先送りをするだけであるから、遺産分割の方法としては最後の手段として選択されるべきものであるとしています。
たしかに、遺産分割は共有状態にある遺産を各相続人に取得させることによって共有状態の解消を図るものですから、共有分割では何も解決されません。
共有分割を行い、解決を先送りにしているうちに、どんどん世代が変わるごとに相続人が増えていき、さらに解決が困難となってしまいます。
そのため、遺産分割事件において、裁判所や弁護士は、日頃からなんとか共有分割ではなく現物分割、代償分割、換価分割で解決できないかと四苦八苦しています。
3 まとめ
このように、遺産分割の方法を検討するに当たっては、安易に共有分割で終わらせることを選択するのではなく、他の分割方法で解決する方法を模索していくことが重要です。
以上