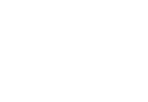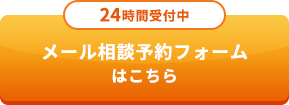【弁護士による判例解説】「前の遺言と抵触する遺言等がなされた場合」
1.遺言の撤回
遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。
また、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされ(同法1023条1項)、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合についても、その抵触部分については、遺言を撤回したものとみなすとされています(同条2項)。
このように、後の遺言や生前処分その他の法律行為が、前の遺言と抵触する場合には、前の遺言を撤回したものとみなされますが、何をもって「抵触」するといえるのか、という点で紛争を生じることがあります。
この点について、以下の判例を紹介いたします。
2.最高裁昭和56年11月13日判決
(1) 事案の概要
AB夫婦は、昭和48年12月22日、終生AB夫婦を扶養することを前提に、Xらと養子縁組を行い、同月28日、不動産のほとんどをXらに遺贈する内容の公正証書遺言を行いました。
しかし、昭和49年10月、X1が、自身の経営する会社の4億円の借入金の担保として、Aに無断で遺贈の対象となっている不動産に根抵当権を設定していたことが発覚しました。
それを知ったAは激怒し、X1は上記根抵当権の抹消と会社がAから借り入れていた1500万円の返還を約しましたが、その約束は履行されませんでした。
そこで、AB夫婦は、Xらに不信感を持つようになり、昭和50年8月、AB夫婦とXらとの間で協議離縁が成立しました。
その後は、Xらは、AB夫婦を扶養することはなく、専らAの実子(婚外子)であるY1がAB夫婦の身の回りの世話をしていましたが、昭和52年1月、Aが死亡しました。
なお、離縁後、A死亡までの間に、Aは公正証書遺言を取り消すことはありませんでした。
Aの死亡後、Xらは、Y1らAの相続人に対して、遺贈を受けたことを根拠として、不動産の所有権移転登記手続を請求しました。1,2審ともに、遺贈と離縁の「抵触」を認め、遺言が撤回されたものとして、Xらの請求を棄却したため、Xらが上告しました。
(2) 裁判所の判断
民法1023条の法意は、遺言者がした生前処分に表示された遺言者の最終意思を重んずるにあることはいうまでもないから、同条2項にいう抵触とは、単に、後の生前処分を実現しようとするときには前の遺言の執行が客観的に不能となるような場合にのみとどまらず、諸般の事情より観察して後の生前処分が前の遺言と両立せしめない趣旨のもとにされたことが明らかである場合をも包含すると解するのが相当である。
AはXらから終生扶養を受けることを前提としてXらと養子縁組をした上でその所有する不動産の大半をXらに遺贈する旨の遺言をしたが、その後Xらに対し不信の念を深くしてXらとの間で協議離縁し、法律上も事実上もXらから扶養を受けないことにしたというのであるから、右協議離縁は前に本件遺言によりされた遺贈と両立せしめない趣旨のもとにされたものというべきであり、本件遺贈は後の協議離縁と抵触するものとして前示民法の規定により取り消されたものとみなさざるを得ない。
3 まとめ
上記の通り、民法1023条2項により、生前処分その他の法律行為が前の遺言と抵触する場合には、前の遺言を撤回したものとみなされます。
そして、この「生前処分その他の法律行為」は、必ずしも財産上の処分である必要はなく、離婚、離縁などの身分行為も含まれると解されています。
ただ、前の遺言と後の行為とが「抵触」するかどうかについては、上記の判例の規範からも分かる通り、一義的に明確であるとはいえず、争いを生じやすい部分です。
したがって、遺言があるところに、別の遺言をしたり、遺産を生前処分したりしようとする場合には、後の遺言や処分行為等に先立って、まずは前の遺言を撤回しておくことが大切です。
以前遺言書は作成したけれど、遺言書の内容を一部変更したり、別の内容の遺言書を作成することをお考えの場合には、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
以上