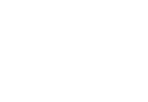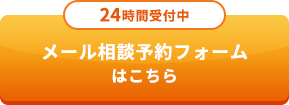【弁護士による判例解説】「遺留分侵害額請求と消滅時効を止める方法」最高裁判所平成10年6月11日判決 東京地裁令和元年9月19日判決
今回は、遺留分侵害額請求と消滅時効を止める方法について解説します。
1 遺留分侵害額請求の消滅時効
遺留分侵害額請求の消滅時効は、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。」とされています(民法1048条前段)。
また、遺留分侵害の事実を知らなくても、相続の開始を知ってから10年間が経過したときはもはや遺留分の請求が出来なくなります(除斥期間、民法1048条後段)。
そして、一度、遺留分侵害額請求を行うと、相手方に対する金銭請求権となりますが、意思表示から5年で消滅時効にかかりますのでお気を付けください(民法166条1項1号、※但し、民法改正により2020年4月1日以降の行使の場合)。
2 消滅時効を止める方法
遺留分の権利行使は、配達証明付内容証明郵便で行うのが一般的です。
端的にいえば、「自分は遺留分の請求をしたい。」という意思が伴った言葉や行動があれば、「遺留分の権利行使」というのは出来ますが、裁判などでは遺留分の権利行使を行ったことの証拠が必要になります。
もし、口頭や配達の証明がない普通郵便でこれを行った場合に、相手方から、そのようなことを言われた事実はない、とか記憶にないと言われてしまうと、立証する方法はなくなってしまいます。
そのため、その手紙が配達された事実と、手紙に書かれている内容を郵便局が証明してくれる「配達証明付内容証明郵便」というものを使用するのが無難ということになるのです。
3 裁判所が認めた意思表示の方法
(1)事案の概要
最高裁判所10年6月11日判決は、平成6年2月9日に公正証書遺言を受け取り、自らの遺留分を侵害する遺贈の存在を知り、同年9月14日に代理人弁護士が「貴殿のご意向に沿って分割協議をすることにいたしました。」と普通郵便を送付し、相手方が受領したあと、同年10月28日に遺留分減殺(※民法改正前の事案のため遺留分侵害ではなく遺留分減殺とされています)の内容証明郵便を送付したが、相手方が多忙を理由に受領出来ず、遺留分の記載がある通知書については、1年経過後の平成7年3月14日に代理人の弁護士による手紙が最初に到達した手紙となってしまった案件について、以下の通り判示しました。
(2)裁判所の判断の要旨
ア 遺産分割と遺留分減殺は、要件、効果を異にするから、遺産分割協議の申し入れに当然に遺留分減殺の意思表示が含まれているとすることは出来ない。
イ しかし、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるには法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争事ことなく、遺産分割協議の申し入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申し入れには、遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当である。
(3)判例考察
この最高裁判例は、遺産分割協議の申入れに、遺留分侵害額請求の意思表示が含まれていると判示していますが、これは救済のための事例判例的に取り扱われています。と、申しますのも、本件は、実際には受取人が多忙のために受領しなかったため、到達こそしなかったものの権利者が遺留分減殺の内容証明郵便を送付していますし、相手方も他の弁護士に法律相談をして今後遺留分減殺の可能性があることなどを聞いていたため、当事者双方が遺留分減殺を前提に行動していたことなどが背景事情としてあります。
そのような法解釈を正当化できる事情をもとに、形式的には遺産分割の申し入れであっても、遺留分減殺の意思表示まで含むと判断したと考えられています。
実際に、東京地方裁判所令和元年9月19日判決では、遺言を無視して自らに大半の遺産を相続させるべきと遺産分割で主張した事案につき、遺産分割の申入れや、その調停の申立てには遺留分減殺の意思表示は含まないと判断しています。
(4)まとめ
やはり、遺留分の消滅時効を止めるためには、配達証明付の内容証明郵便を利用するのが最善ということになります。
以 上