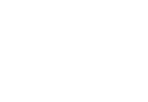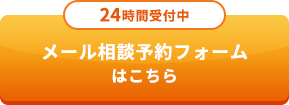【弁護士による判例解説】「成年被後見人の遺言」 名古屋高等裁判所平成9年5月28日判決
認知症等によって認知機能が低下し、事理弁識能力を常に欠く状態となった場合、親族等の請求によって、家庭裁判所による後見の審判を受けます(民法7条)。
原則として、15歳以上の者であれば遺言することができますが(民法961条)、成年被後見人が遺言書を作成する場合は、事理弁識能力が一時的に回復したときに、医師が二人以上立ち会い、「遺言をするときに事理弁識能力を欠く状態になかった」と付記することが必要です(民法973条)。
もっとも、これは形式的な要件の話であり、医師の立ち会いと付記があれば、遺言の有効性が確定するわけではありません。医師の立ち会いのもとで作成した遺言書でも、後にその有効性が争われた場合には、診療録等から、遺言作成時の状態を判断する必要があります。
1 事案の概要
被相続人であるAは、昭和58年3月、「全ての財産を二女Yに相続させる」という内容の公正証書遺言を作成しました。
その後、昭和59年4月、Aは、多発性脳梗塞の影響により認知機能、判断能力が低下していたため、後見(当時は「禁治産宣告」という名称の制度でした。)の審判を受けました。
そして、昭和59年11月、Aは医師二人の立ち会いを受け、「事理弁識能力を欠く状態にはない」という付記を得て、「全ての財産を妻Bに相続させる」という、昭和58年遺言と抵触する内容の公正証書遺言を作成しました。内容の抵触する遺言が複数存在する場合、後に作られた遺言によって、前に作られた遺言は取り消されるのが原則です。
被相続人Aが亡くなった後、二女Yは、昭和58年遺言に基づいて、Aが所有していた不動産の名義を自身に移しましたが、それに対して、昭和59年遺言の遺言執行者であるXが、二女Yに対して、所有権移転登記の抹消手続きを求める訴訟を提起しました。
その訴訟の中で、被告である二女Yは、「昭和59年遺言の作成当時、Aは遺言能力を欠く状態であったため、無効だ。」と主張しました。
2 名古屋高裁判決の概要
裁判所は、名古屋地方裁判所岡崎支部の第1審も、名古屋高等裁判所の控訴審も、いずれも、昭和59年遺言は有効であるとして、登記の抹消請求を認めました。
遺言作成時の被相続人Aの遺言能力に関しては、見当識障害や記憶障害の症状はあったものの、多発性脳梗塞による知的能力の低下は一時的な改善が期待できること、公正証書作成当時の受け答えの様子、遺言の内容が「全てを妻に相続させる」という単純なものであったことなどから、遺言能力はあるものと判断されています。
3 本件の解説
民法973条という規定はありますが、後見の審判を受けた方が、一時的にでも能力を回復することは稀であり、実際に利用される場面は少ないと思います。
基本的には、後見開始の審判を受けた後で、有効な遺言を作成することは難しく、また、後見開始の審判を受けていなくても、認知症等の状態によっては、後に遺言は無効だったと判断される可能性があります。
遺言を作成するのであれば、認知機能が低下する前に、しっかりと自身の意思を残しておくことが肝要です。