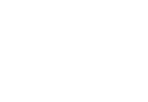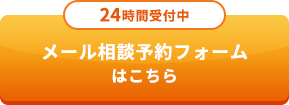【弁護士による判例解説】「自筆証書遺言の要件を満たさず無効な遺言が死因贈与契約の証拠となるか。」
自筆証書遺言は、法律の専門家のアドバイスなく作成されることが多い遺言です。
そのため、無効とされるケースがあるのですが、遺言能力ではなく、例えば、遺言書の形式的な面(押印がないことや自書等の要件)で無効となった場合には死因贈与契約の証拠の一つとして認定され、結果として救済されることがあります。
1 最高裁判所昭和32年5月21日判決
(1)事案の概要
X(被上告人)は不動産Aを所有し、同所に居住していたところ、昭和6年2月に競売に遭い、Y(上告人)の元養父Zが競落して所有権を取得しました。
Zは家庭内の不和から自らの家の将来を案じ、昭和14年10月30日に親戚の間柄であったXに対し、自分が死んだときには不動産AをXに贈与することを確約し、同旨の自筆証書遺言を残していたという事案です。
(2)裁判所の判断
ア 福井地方裁判所敦賀支部
第1審は、本件自筆証書遺言が、Zの自筆以外の部分が含まれており、自筆証書遺言の要件を満たさないことを理由に無効としました。
イ 名古屋高等裁判所金沢支部
第2審の名古屋高裁は、遺言については、Xがあり合わせの用紙に下書きしたものに、Zが清書をせずにそのままなぞって署名押印したものであるところ、「遺言証書」とあるのはXの法的無知によるものであり、実質は死因贈与の趣旨であったと解釈し、かつ、XとZの生前の関係性、死因贈与に至る経緯、死因贈与の内容がZの全ての遺産からすればわずかであることなどから総合的に考慮して、本件遺言は死因贈与契約をなすものだと認定し、不動産AがXに帰属することを認めました。
ウ 最高裁判所昭和32年5月21日判決
最高裁は、死因贈与契約については、遺言の方式に従う必要はなく、一般的な契約の方式に依拠すると判示し、名古屋高裁の判断を是認しました。
2 考察
遺言を残す際には必ず、公正証書遺言にて作成することをお勧めしています。
自筆証書遺言と異なり、公証人という遺言の専門家が作成しますから、方式で無効となることはまず考えにくいですし、認知症などで遺言能力が疑われる場合にも、公正証書遺言が作成できれば無効とされる可能性は限りなく低くなります。
しかし、実務上は、手軽な自筆証書遺言もよく用いられています。この場合、要件を満たさずに無効となったり、遺言能力を争われることがよくあります。
今回、ご紹介した案件は、自筆証書遺言としては無効となった書面についても、死因贈与契約として解釈することが出来ないかという判例になります。判例はこれを肯定したわけです。
死因贈与契約は口頭でも成立しますから結論としては相当としても、あまり際限なく認めてしまうと、厳格な要件を定めている遺言制度の趣旨を潜脱することにもなりかねないですから、例えば、遺言書の無効とされる理由が軽微なものに止まり、死因贈与の意思が明確に読み取れること、生前の関係性からそのような死因贈与契約をすることが相当であること、贈与される資産の性質、その他の相続人の関係など丁寧に認定する必要があるように思います。
当職も過去に、遺言書の作成途中で被相続人が亡くなり、口頭で負担付きの死因贈与を約束されていた方から受任し、相続財産管理人を相手に負担付き死因贈与契約の履行請求を行ったことがありますが、やはり似たような要素を立証することで、勝訴することとなりました。
遺言が間に合わなかった、あるいは、遺言があるけれども無効とされてしまった場合でも、死因贈与と解釈することが出来ないか、一度ご検討されると良いかもしれません。
以 上