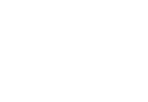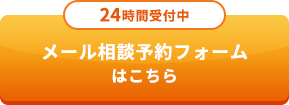【弁護士による判例解説】「特別寄与料をめぐる問題」
1.特別寄与料の制度の新設
被相続人の家業を無償で手伝っていたり、療養看護を行っていたなど「特別の寄与」をした相続人には、寄与分が認められ、当該相続人は、その分だけ他の相続人より多くの遺産が取得できることになります。これが寄与分制度です。
ただし、寄与分は、相続人でなければ認められません。
したがって、例えば、両親と息子夫婦が同居しており、父親に介護が必要になったが、その介護を行っていたのは専ら息子の妻であったような場合、父親が死亡してもその妻は父親の相続人ではないため、寄与分の主張はできません。このような場合、相続人である息子と妻の貢献を一体としてみて寄与分を評価することはできますが、財産を取得するのはあくまでも相続人です。
また、息子が父親より先に亡くなり、代襲相続人もいないような場合は、そもそも相続人の相続分が存在しないため、妻の貢献は全く評価されないことになってしまいます。
そこで、平成30年の民法改正において、特別寄与料の制度が新設されました(民法1050条)。
2.特別寄与料が認められる要件
(1) 請求権者
被相続人の親族です。親族とは6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族のことをいいます(民法725条)。
ただし、相続人、相続放棄をした者、相続欠格、廃除により相続権を失った者は除かれます。
(2) 特別の寄与の存在
①被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、②被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたことが必要です。
(3) 期間制限
特別寄与料について当事者間の協議で話がまとまらない場合は、裁判所へ協議に代わる処分(調停・審判)を請求することになりますが、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過した時又は相続開始の時から1年を経過した時は請求できません。
3.問題点
上記のとおり、特別寄与料が認められるためには、「特別の寄与」が必要であり、また、協議がまとまらない場合の調停・審判の申立は、「相続人を知った時」から6か月又は相続開始の時から1年を経過する前であることが必要となります。
以下では、これらの文言の解釈に関する裁判例を紹介します。
4.静岡家庭裁判所令和3年7月26日審判
(1) 事案の概要
被相続人Aは、夫Bと離婚し、子Y1、Y2がいますが、Y1、Y2とは長年疎遠でした。Xは、Aの弟です。Xは、Aの死亡前からY1、Y2の存在や氏名は知っており、さらにY2については住居も知っていました。
Aが令和2年3月に死亡したため、Xは、Y2の住居を訪れ、郵便受けにAの死亡の事実や葬儀の日程等を記載した手紙を入れました。
また、Xは、同年5月以降、Aの遺産である預貯金の解約等の手続を進め、その間、少なくともY2とは連絡を取っていました。その中で、Xは、上記解約等の手続に必要な書類であるとして、Y2から委任状や印鑑登録証明書、戸籍謄本を取得し、同年8月16日頃には、Y2を介して、Y1からもこれらの書類を取得しました。
その後、Xは、Aの入退院時の手続きや、付添、必要品の購入・準備、書類作成・提出、医師の説明の際の立会いや呼び出しに対する対応を行っていたことから、Aの遺産の3分の1を取得したい旨をYらに伝えましたが、Yらから拒否されました。
そのため、Xは、令和3年1月20日、Yらに対する特別の寄与に関する処分調停をそれぞれ申し立てましたが、調停は不成立となり審判に移行しました。
(2) 裁判所の判断
Xの主張を前提としたとしても、月に数回程度入院先等を訪れて診察や入退院等に立ち会ったり、手続に必要な書類を作成したり、身元引受をしたりといった程度にとどまり、専従的な療養看護等を行ったものではなく、「特別の寄与」の存在を認めることは困難である。
また、民法1050条2項にいう「相続人を知った時」とは、当該相続人に対する特別寄与料の処分の請求が可能な程度に相続人を知った時を意味するものと解するのが相当であると判示し、Xの申立を却下しました。
(3)考察
寄与分における「特別の寄与」は、寄与の程度が被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度の貢献を超える高度なものであることが要求されます。
一方、特別寄与料の請求者は扶養義務を負わない親族まで含まれることからすれば、特別寄与料の「特別の寄与」は、寄与分のような高度な貢献までは要求されず、ある程度の貢献があれば認められると考えられます。
しかし、本件においては、Xは、入退院時の事務手続等を行っただけであり、療養看護行為自体を行ったのではないことから、Xの行為は「療養看護その他の労務の提供」には該当しないと判断されました。
なお、Xは、Aの死亡後に葬儀等の手続をしたことも「特別の寄与」にあたると主張しましたが、この点については、そもそも、「特別の寄与」として考慮しうるのは相続開始時までの行為、すなわち生前のものに限られるとしてXの主張を退けています。
また、「相続人を知った時」について、Xは、相続人の氏名及び住所を正確に知った時を意味するという主張をしましたが、裁判所はそこまでは必要ないとして、Xの主張を退けています。
したがって、例えば、相続人の1人と連絡がついており、その相続人を介して他の相続人の住所等を聞き取るなどして調査することが容易な状態であれば、その時点で、他の相続人についても「相続人を知った時」と言えると考えられます。
まとめ
特別寄与料については、請求権者、要件は条文で定められていますが、どのような行為が「特別の寄与」と認められるかは一義的に明確ではありません。
また、その請求には6か月(若しくは1年)という期間制限も定められていることから、特別寄与料の請求をお考えの場合は、できる限り早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
以上