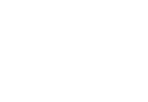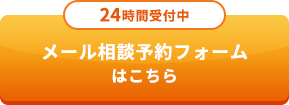【弁護士による判例解説】「相続放棄の熟慮期間の起算点」
1 相続放棄
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に行わなければならないとされています(民法915条1項本文)。
それでは、生前、被相続人と疎遠であり、被相続人の財産状況を一切把握していなかったため、相続放棄をすることなく3か月が経過したものの、その後に被相続人に多額の債務があることが判明したような場合、相続放棄をすることはできるでしょうか。
2 最高裁昭和59年4月27日判決
(1)事案の概要
Xは、Bに対する1000万円の貸金の連帯保証人であるAに対して連帯保証債務の履行を求める訴訟を提起し、第一審で勝訴判決を受けましたが、その判決がAに送達される前にAが死亡したため、訴訟手続は中断しました。
そして、Aの死亡後1年近くを経過した後、Xの申立を受けて、裁判所はAの相続人である子Yらに訴訟を受継させて、判決を送達しました。
Yらは、10年以上にわたりAとは没交渉でした。YらはAの死亡の事実はすぐに知りましたが、本件訴訟についてはもちろん、その生活状況も資産や負債についても一切知りませんでした。
そのため、YらはAの資産は全くないと考え、相続に関しての手続をとらずに放置していました。
ところが、Yらは、Aの死亡後1年近くを経過した後に、上述の通り、第一審の判決の送達を受けて初めて本件連帯保証債務の存在を知りました。
そこで、Yらは、判決に対して控訴の申立をする一方、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理されたため、相続放棄の申述が有効か否かが争われました。
(2)裁判所の判断
Yらは、Aの死亡の事実及びこれによって自己が相続人となった事実を知った当時、Aの相続財産が全く存在しないと信じ、そのために当該各事実を知った時から起算して3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったものであり、しかも、Yらが本件第一審判決正本の送達を受けて本件連帯保証債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であって、相続財産が全く存在しないと信じるについて相当な理由があると認められるから、民法915条1項本文の熟慮期間は、Yらが本件連帯保証債務の存在を認識した時点から起算されるとし、Yらの相続放棄の申述は熟慮期間内になされた適法なものであって、これに基づく申述受理も適法である判示しました。
(3)考察
民法は、上記のとおり、相続放棄の熟慮期間の起算点について、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とのみ定めています。
この文言からすれば、熟慮期間の起算点については、当該相続人の相続財産の存否に関する認識は考慮されないようにも思われます。
しかし、下級審裁判例や学説は、「自己のために相続の開始があったことを知った」といえるためには、相続財産の存否を覚知したことが必要と考えるものが多数でした。
もっとも、その認識を必要とする遺産の対象については、「なんらかの遺産の存在」、「積極財産の一部又は消極財産の存在」等様々でした。
このような中で、最高裁は、本判決で、熟慮期間の起算点として、原則として、相続開始の事実と自己が相続人となった事実を知れば足り、遺産の存否の認識は影響ないが、例外的に相続人が相続財産が全くないと誤信していたために相続放棄の手続をとる必要がないと考えて熟慮期間を徒過した場合には、その誤信につき過失がないことを条件に、起算日を遺産の認識時又は認識可能時に繰り下げることができるとしました。
本判決が「相続財産が全く存しないと信じ」たために3か月以内に相続放棄をしなかった、と述べていることから、本判決の射程は、相続人が積極・消極ともに存在しないと思っていた場合に限られ、積極財産の存在は認識していたものの消極財産については存在しないと誤信していた場合には当然には及ばないと考えらます。
学説は、①相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた場合に限られるとする見解(限定説)、②一部の相続財産は知っていたが、通常人がその存在を知っていれば相続放棄をしたであろう債務が存在しないと信じた場合も含まれるとする見解(非限定説)に別れていますが、本判決のとおり、最高裁は、限定説をとり、その後も一貫して限定説を採用しています(最高裁平成13年10月30日判決)。
このことからすれば、何らかの遺産が存在することを認識した若しくは認識できた以上は、仮に負債の存在が判明していなくても、その時点で熟慮期間の進行が始まると考えておくべきです。
もっとも、下級審の裁判例の中には、非限定説をとるものもあり、事情によっては、相続放棄が認められる可能性もあると考えられます。
したがって、相続放棄をしないでいたところ、後になって被相続人に多額の負債があることが判明した場合は、すぐに諦めず、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
以上